ステルスマーケティングってなに?気をつけるべきポイントをわかりやすく解説!

最近、ネットやテレビで「ステルスマーケティング」という言葉をよく聞きますよね。
でも、具体的に何を指すのか、どうして注意が必要なのか、ちょっとわからないかもという方も多いのでは?
 こんた
こんた友人のハンドメイド作家さんからもご相談をもらったので、今日は、この「ステルスマーケティング」について、できるだけわかりやすく解説してみようと思います!
ステルスマーケティングってなに?
「ステルスマーケティング」とは、広告や宣伝を、それが広告だと分からないように紹介する方法のことを言います。
たとえば、友だちが「このお菓子、おいしいよ!」ってすすめてくるとき、それが実はお店からの頼みで言っている場合、それはステルスマーケティングの一つです。
ステルスって、隠れるという意味があるんだよね。
だから、ステルスマーケティングは、広告や宣伝を、「ひっそりと」それが広告だと分からないように伝える方法。
イメージとしては、友だちが新しいゲームをすすめてくるけど、それが実はゲームの会社からのお願いで言っている…みたいな感じかな!
どうして気をつける必要があるの?
2023年10月1日から、景品表示法によりステルスマーケティングは法律で厳しくなりました。
簡単に言うと、ステマ規制では、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示が禁止されます。
つまり、消費者が広告だと見分けられない表示が法規制の対象となります。

今のところ、規制の対象は広告主であり、インフルエンサーなどの宣伝者は対象になりませんが、インフルエンサーや従業員の過去のSNSの書き込み、事業者のWebサイト内の記述などが対象なんです。
違反があれば、広告主企業に罰則が科される場合があり、企業イメージの失墜や顧客離れにつながる恐れがあります。
それは、みんなが正直な真実の情報だけで商品やサービスを選べるようにするためなんだけど。
隠れた宣伝をされると、本当にその商品が良いのか、それとも宣伝のために言っているのかがわからなくなってしまうからです。
隠れて宣伝されて、後で「えっ、これ宣伝だったの?」ってなるのは、ちょっとショックだよね。
景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るためにある法律です。
ステマ規制の対象となるのは?
- インターネット上の表示すべて
- SNS投稿
- レビュー投稿など
- テレビ、新聞、ラジオ、雑誌等の表示なども

ステマ規制に該当する可能性がある場合は、内容の修正や削除などの対策をとる必要があります。
ハンドメイド作家でも起業家でも
自社製品を投稿するときのSNS運用に関する注意点
インスタやツイッターで自分の作品や商品を紹介すること、それはすごく素敵なこと!
でも、その紹介が宣伝目的だったら、ちゃんと「これ宣伝です!」って伝えることが大切になってきたんです。
例えば、自分の作った手作りのバッグを「手作りしました~!」とか「新作完成」「新色出ました🎉」って紹介するだけなら大丈夫。
でも、「このバッグ、今ならセール中!早くゲットしてね!」って言う時は、宣伝だってことをしっかり伝えなくちゃいけないみたい。
自分が作った商品でもSNSに紹介するとき、それが宣伝目的であれば、ステルスマーケティングの対象になり得ます。
自分の作品を紹介するだけで、特定の商品やサービスの購入を促すような言葉を使わなければ、問題はないかもしれないけど。
でも、商品を販売するためのリンクを貼ったり、購入を促すような言葉を使う場合は、その投稿が宣伝であることを明確に伝えた方が良いと思う。
「今すぐ買ってね!」というような言葉を使う場合は、その投稿が宣伝であることをちゃんと伝えてきましょう!
ステルスマーケティングは、隠れた宣伝の方法。
だからこそ、最近の法律の変更で、その「隠れた」部分がちょっと難しくなったよ。
SNSやホームページで情報を伝える時、正直で分かりやすい情報を提供することが大事だよね。
みんなが、楽しく安心してネットの情報を楽しめるように、このルールを守っていきましょう~!
ステルスマーケティングに関する法律は過去の投稿も対象か?
ステマ規制は、2023年9月30日以前に掲載された「過去に発信したものも対象に」なったので、過去に投稿したりホームページに掲載している情報も対象となります。
インターネット上の情報は、10月1日以降も閲覧可能な状態であれば規制対象となります。
たとえば、インフルエンサーや従業員の過去のSNSの書き込み、事業者のWebサイト内の記述などが対象です。
つまり規制強化にともない、10月以降に発信する広告やPRだけでなく、これまでに発信してきた投稿、レビューなどもステマ行為に当てはまらないかのチェックが必要だということになります。
もし、これらに該当するものがあれば、内容の修正や削除といった対策をとる必要があります!
ステマ規制に引っかからないための施策は?
発信者と事業者との関係性を明らかにしよう
ステマ規制の対象だとみなされるポイントは2つあります。
- 商品やサービスを提供する事業者による表示であること
- 事業者による表示であることを、一般消費者が判別するのが困難なものであること
そのため、一般消費者が自発的に購入した商品やサービスについて、自身の感想や口コミを発信(表示)する分にはステマ規制の対象外です。
ただし、発信や発信内容について事業者が関わっていれば、たとえ発信者が一般消費者だとしても不当表示に該当します。
規制に触れない対策は?
「この表示は広告や宣伝であり、事業者から依頼を受けて発信した内容であるという事実」
「発信者と事業者との関係性」を明らかにすることです。
例えば、インスタやFacebookなどのSNS投稿では「#PR」「#タイアップ広告」「商品提供:●●社」といったハッシュタグやフレーズを入れる方法があります。
またYouTubeでは、動画を公開する際に有料プロモーションが含まれている旨を申告すると、自動的に「この動画はプロモーションを含みます」の一文が表示される仕様となっています。
このように、ステマ規制に合わせたガイドラインが定められているSNSも増えつつあります。
ぜひ活用していただきたいのが、消費者庁が公開しているガイドブック『景品表示法とステルスマーケティング』の資料です。
ステマ規制を回避するための、注意する必要があること
- 広告であることを明示する
- ハッシュタグで「#PR」などの推奨タグをつける
- 依頼されていることを隠さない
- 一般消費者として商品を使っていることを装わない
- 商材やサービスを提供している企業・ブランドとの関係を明示する
たとえば、書籍の献本の感想を投稿する場合は、「献本された」とわかるように表示する必要があります。
ホームページ保健室
「ホームページがわからなすぎる」とひとりで悩んでいませんか?
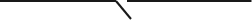
法人~個人まで2,500サイトを制作したWebサイト制作技術の専門家が、
ホームページの技術的なこと~運用方法まで、
なんでも解決する『ホームページ保健室』をご利用ください。
\ 何日も悩んでいたことが、一瞬で解決 /


































